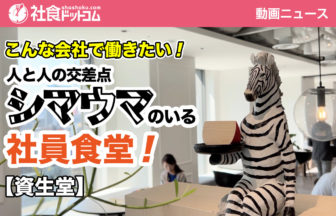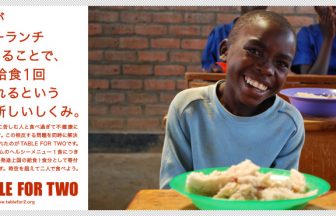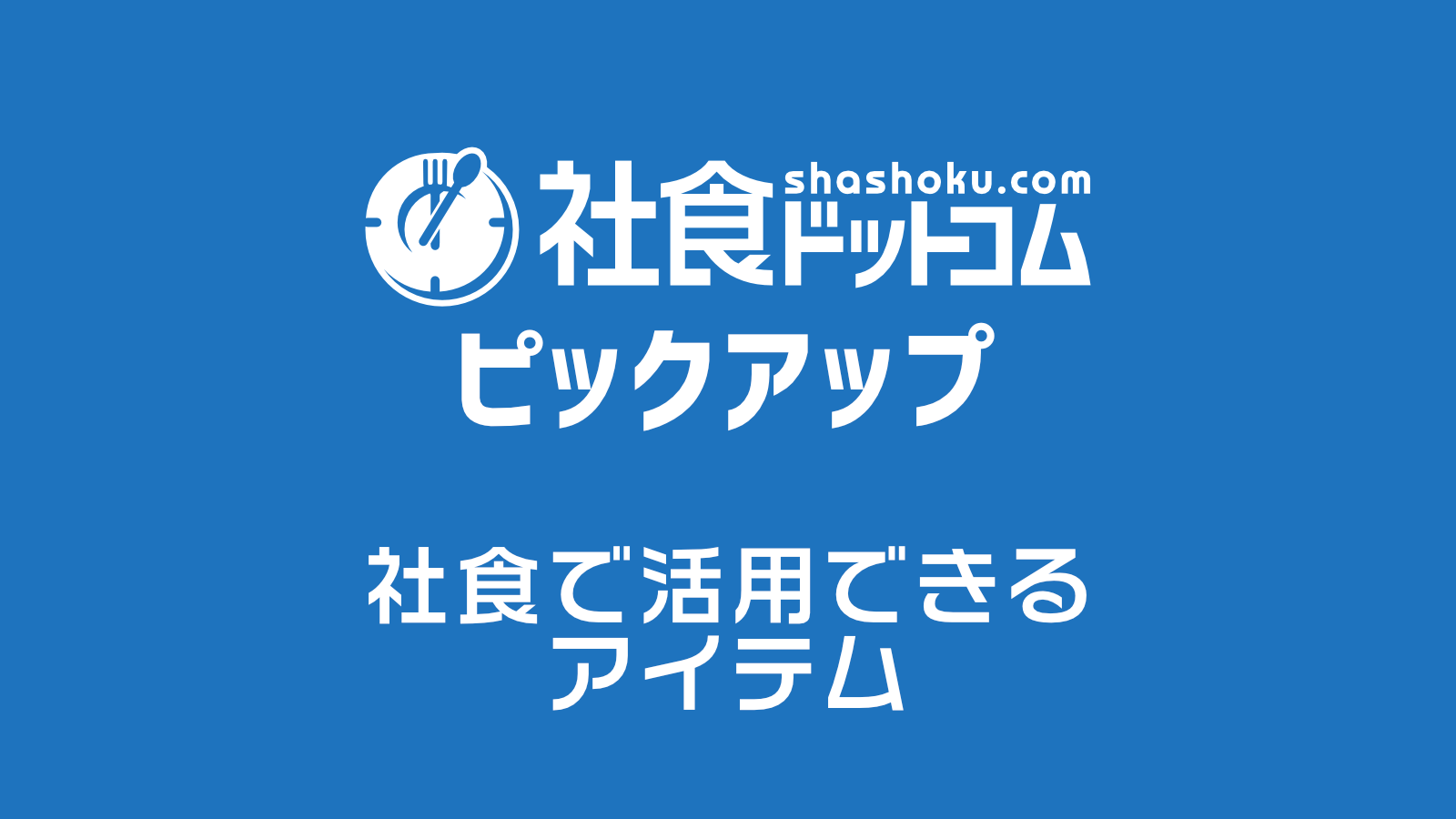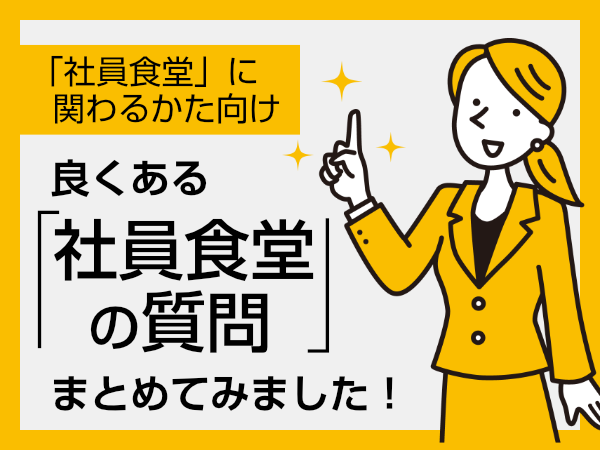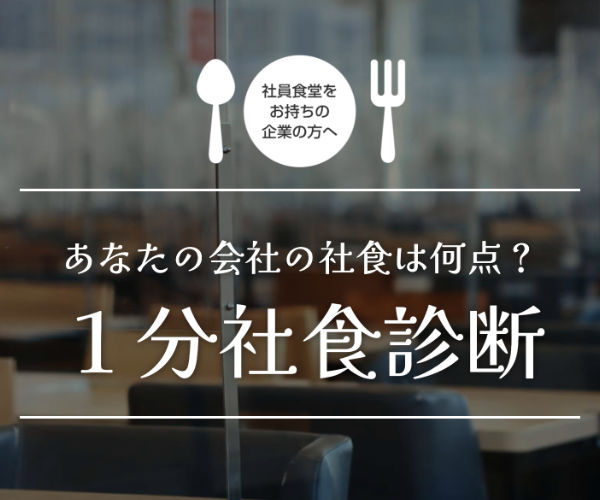新型コロナウイルスの影響で、新しい働き方や生活様式の変化が起きています。たとえばテレワークが常態化することは、企業で働く人にとって「社員食堂」の利用度が減ることにつながる・・・など、社員食堂業界も大きな変化の真っ只中にいます。
一方で社員食堂が担ってきたコミュニケーションの場としての役割などが、企業内で大きな意味を持っていたことが判明するなど、あらためてその価値が見直されつつあるという一面も浮かび上がってきています。
そこで社食ドットコムでは、社員食堂に熱視線を送る各業界の方にお話しを伺い、これからの社員食堂の方向性に注目している人や羅針盤となるキーパーソンにお話を伺っています。
今回お話を伺ったのは、食堂とは切っても切れない関係の厨房機器のリーティングカンパニーであるタニコー株式会社の谷口社長。コロナ禍における厨房機器業界の現状や社員食堂業界に期待することなど、貴重なお話しをいただきました。
<敬称略 聞き手 社食ドットコム編集部>
プロフィール
谷口秀一(TANIGUCHI,Shuichi)/タニコー株式会社 代表取締役 社長
1961年東京都生まれ。武蔵野音楽大学を卒業後、株式会社DTSを経て、1986年株式会社タニコーテック入社、2006年タニコー株式会社に移籍、2010年社長就任。現在に至る。趣味はピアノ演奏(最近のマイブームはラフマニノフ)。クラブ・プロスペール・モンタニェ日本支部会員。
会社概要
タニコー株式会社。1946年創業、本社を東京都品川区に置き、資本金5億2千万円、全国94箇所の営業所、7工場(関連会社には4工場)、従業員数1,556人(2020年3月末時点)、年商477億円(2020年3月期)という業務用厨房機器及び関連機器各種の国内最大手メーカー。
https://www.tanico.co.jp/

Q1 コロナ禍における厨房機器市場はどのような状況でしょうか?
谷口 2020年、日本に新型コロナウイルスの感染拡大が始まると同時に、外食各社は混乱しました。クライアント企業も出店や設備投資どころではなくなってしまい、弊社自身も大きな影響を受け、設備提案を行なうよりも顧客との関係維持を最優先に営業活動を行なうなど、業務全体を大きくシフトせざるを得ませんでした。
このようにビジネス的には2020年は混乱しました。他の厨房機器メーカーも同様だったでしょう。特に飲食業界はお店を開けようか閉めようかどうしようか、と右往左往していましたので、厨房機器どころではなかったことでしょう。このように弊社の大きなクライアントである外食産業業界にも激震が走りました。
その後、飲食店にとっては、安心・安全の取り組みイコール集客、になっていますが、これは飲食店を利用するお客様が「この店ではこういう安全が担保されている」「機械化されている」「アクリル板や換気設備がある」といった対策が取られているお店に対して、「清潔そうだ」「安全なお店だ」と判断することが当たり前になったためで、それがイコール選ばれるお店に繋がっているわけです。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響がなかった2019年まで、日本では安心・安全は無料でした。安心・安全のための製品開発をしても、それは付加価値にはなりにくかったといえます。
しかし、2020年以降イヤというほどいろんな経験をしました。私が重要視しているのはコロナ禍で何が変化したのか? ということですが、コロナ禍を経て、安心と安全はお金を出して設備するものなんだというように、社会の意識が変わりました。これが一番大きな転換点と言えるでしょう。
そんなコロナ禍を経た2021年9月現在、飲食業界の動きは、水面下では元に戻ってきています。特に全国チェーンの外食店、誰もが知っている牛丼屋さんというような大規模展開の外食チェーン店が、すでに設備投資・出店の方向に戻って来ています。それが外食産業全体としては大きな息吹で、業界の牽引になっています。
また、出店する際の厨房機器の選択にも変化が現れています。たとえばある大規模洋食チェーン店さんは、コロナ以前は客席が多く、店舗の面積が広かったのですが、「お店が大きいのはリスクだ。面積の大きな店を全国展開すると、今回のようなことがあった時に、持ち帰りや宅配に転換しにくい」となり「それでは小規模店に替えていこう」となるわけです。そうすると厨房も小型化に対応する必要が出てきます。
また、某有名うどんチェーン店さんのように、自動うどん製造機の開発依頼が来るなど、新しいサービスを模索しているのも2021年の特徴で、2021年9月時点では、日常生活においてはまだコロナの影響が色濃く残っていますが、水面下ではどこの会社も生き残りをかけて、アフターコロナのことを考えて手を打っています。
特に明らかなのが、「なるべく人間を使わないで、省人化する」ということで、業界が抱えていた人手不足問題解決にもつながることから、弊社でも大きな可能性を感じています。
Q2 厨房機器メーカーの役割について教えてください
谷口 サイズダウンやロボット化だけでなく、それ以外にも今後続々と案件が出てくると思いますが、クライアントごとに狙いが違うため、そのクライアントが「何をして欲しいのか」を弊社の営業が聞き出すことが一番重要です。
特にこれからの時代は、今まで無かったもの、取り組んでいなかったものを作り出していくわけですから、「こうしてほしい」とハッキリ言えるクライアントは少ない。でも現状を改善していきたいという気持ちは当然ある、という企業がほとんどです。
私たち厨房機器メーカーとしての責任、クライアントへの貢献というのは、どういうことか? その答えは「たたき台をたくさん出していくこと」にあります。クライアントに言われたものを作るだけではなく、「どう言わせるか?」が重要で、クライアントにとって何かヒントになるようなもの、想像力を湧き上がらせるものを提示するのです。
そのためにも展示会などでコンセプト製品を出品しています。それが着想になって、「あれができるんだからこれもできるでしょ」と言うことがあるんですね。クライアントの中にある“種”に水をあげ芽を出させるが私たち厨房機器メーカーにとって重要な役割なのです。
Q3 今後の社員食堂業界について、どのようにお考えですか?
谷口 社員食堂業界の未来は明るいと感じています。その理由として大きいのが、企業の国内回帰志向による工場建設の増加です。
たとえば「人件費が安いから海外進出する」という経営をすると、カントリーリスクをいち企業が負ってしまうことになってしまう。それでは有事の際にリスク回避が難しいということで、撤退まで行かなくても多方面に展開をするというのが潮流となっています。
その中のひとつが国内回帰で、特にその各社のコアになるような技術、主力製品などは国内で生産できるようにしておきたいわけです。先駆けとなったのは2019年の資生堂さんだと思いますが、コロナ以前から国内に大きい工場を作られており、その際に私たちも社員食堂の厨房設備を納めさせていただきました。
この工場を国内に建設する際に問題となってくるのが「人手不足」です。工場の立地は地方が多くなりますが、都会と違って、本来人口が少ない地域に巨大な施設ができるわけです。
工場に適した地域では、多くの企業が自社工場を建設しようと集中します。すると優秀な働き手はその地域で確保しなければいけませんので人材不足が起きます。
ある企業の話では、「工場建設はできても、人集めが大変。相当福利厚生に気を遣わないと集められない」と言います。そこで注目されているのが社員食堂です。
その企業では自社だけでなく、関連会社や下請企業にも工場に入って欲しいとのことで、「それらの企業を説得する際に、傘下企業の社員も自社社員と同待遇にしないと来てくれない」と、社員食堂を目玉にされています。
Q4 社員食堂の「良いところ」はどのようなところでしょうか?
谷口 ひと昔前の「12時にリーンとベルが鳴ると一斉に食堂に集まって、長いテーブルにずらりと座る」というイメージでは無いですね。社員食堂も多目的化して営業時間も長く運用していますし、ご飯を提供する以外の時間帯の活用も盛んになっています。
ある企業では社員食堂にリフレッシュルームと名付けると「気分転換で利用しようとすると、他の社員にサボっているように思われてしまう」と言うことで「ピット」と名付けたそうです。ちょっとピットインしてくる、というイメージをつけた。
そうすると社員が気軽に立ち寄れるようになり、社員さんがお昼を食べてるそこの隣で商談もされていたり、ちょっとしたミーティングやプレゼンをされるなど、ものすごく多目的に使われるようになったそうです。
このように、社員食堂は単に社員の空腹を満たすためだけの施設ではなくなっています。特に働き方が多様になって、同じ会社に所属していても情報を共有することが難しくなっているので、その機能が一番重視されてる施設になっています。何かあった時にパッと集まれる場所として一層重要視されていく施設だと思っていますし、これから力を入れていく企業が増えていくことでしょう。
このように、食事を提供する社員食堂はかなり目立つ施設だと捉えられているため、人材確保の手段としても注目を集めています。
コロナ後は多くの企業の国内回帰が進むでしょうから、すでに国内で工場などの施設建設は増加しています。弊社も大規模な工場の社員食堂の厨房設備を次々と受注しており、2019年と比べると2020年は170%増、2021年は9月時点で前年比100%を達成しています。
Q5 最後にひとことお願いします
谷口 重複しますが、社員食堂はマーケットとして拡大していくと見ています。
おそらく、コロナ禍において、社員食堂を設置しようとする企業というのは相当感度のいい会社だと思います。「テレワークが広がるから、いらないよね」と、尻込みするところもあるかと思いますが、ここがまさに2つの分かれ道です。
感度が高い企業は福利厚生としてだけではない新しい時代にマッチした社員食堂運営を行なっていくでしょう。その動きは感度の高い企業から始まり、その後必要に迫られて取引先や下請けさんが続いて、最後に尻込みしていた会社が遅れてやってくる。他にも社員食堂を設置することの効果が現れた頃、それを見て「やっぱり違った」と慌てて追随する企業も出てくるでしょうが、「時すでに遅し」かもしれないわけです。
社員食堂を運営する会社にとっても、安心・安全を提供する運営の仕方や設備を取り入れていけば、今後感染症と共存することになっても全然問題ないでしょう。時代の変化を捉えていち早く対応することでしょうね。
<終>

社食ドットコム編集部 2021.10