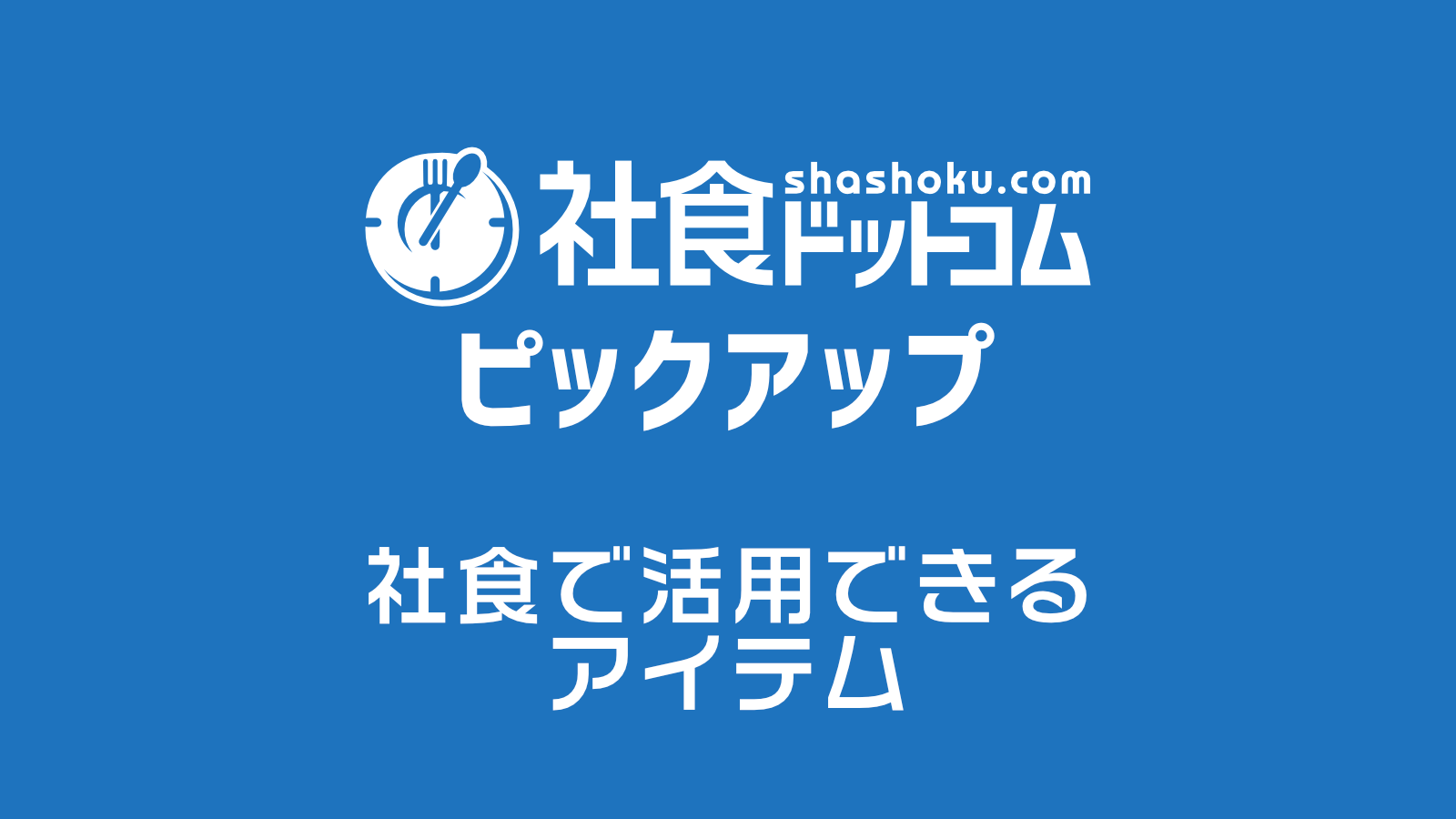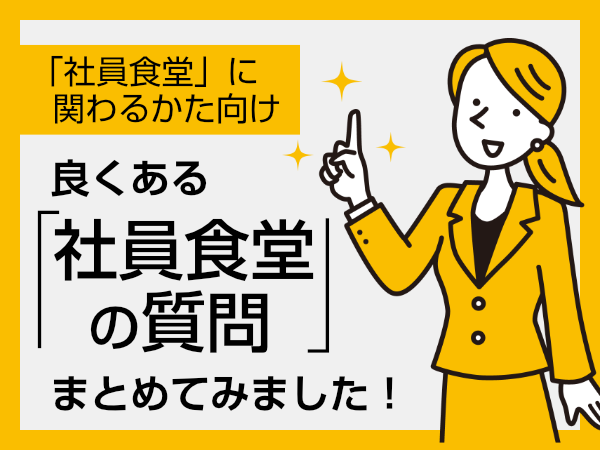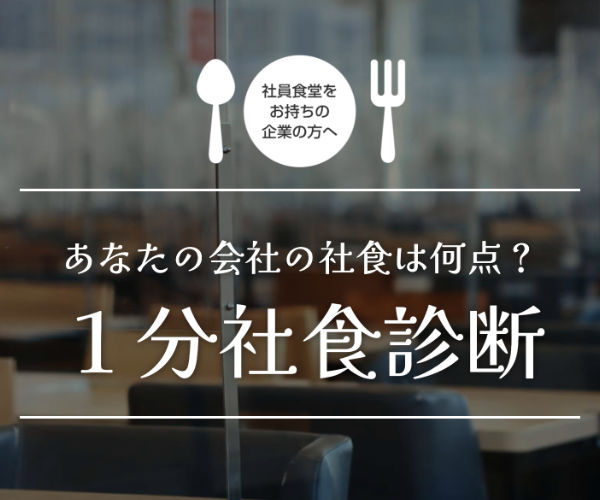昨今は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、出社制限やテレワークの採用が進み、社員食堂そのものの必要性すら問われる時代となっています。しかし不特定多数との接触がないことや栄養バランスの良さ、社員同士のコミュニケーションの場となるなど社員食堂のメリットについてはあまり語られることがなく、社員食堂を有していない企業の方々には、その実情が届いていないことが懸念されます。
このような中、社食ドットコムでは、社員食堂運営会社のトップの方に「社員食堂の良さ」を発信していただき、社員食堂の必要性を社員食堂を有していない企業の方々に理解していただき、社員食堂の市場拡大につなげることが業界全体のメリットに繋がると考えています。
そこで、社員食堂運営業界にて長らく活躍されている社員食堂運営会社のトップの方を直撃取材。「トップが語る、2023年の社員食堂業界」をテーマとして、社員食堂のメリットはもちろん、社長の人となりから今後の社員食堂がどのようになっていくのか? などについてお話をうかがいました。
今回は、株式会社ノンピの上形秀一郎社長です。
【プロフィール】
上形秀一郎(かみがた・しゅういちろう)
株式会社ノンピ代表取締役社長。大学在学中に飲食店の販売促進コンサルティング事業を立ち上げ、起業。事業譲渡後、有限責任監査法人トーマツグループであるトーマツイノベーション株式会社にて、月額定額制社員研修サービスの横浜拠点長、新規事業の立ち上げ等に従事。2014年からは有限監査法人トーマツに転籍し、新規上場企業の発掘、育成業務に従事。トーマツベンチャーサポート株式会社にも籍を置き、シードからアーリーステージのベンチャー支援を行なう。その後、飲食店メディアのスタートアップを取締役副社長として立ち上げた後、上場企業にCMOとして参画。2018年に株式会社ノンピに取締役副社長として経営参画。2022年12月より代表取締役社長を務める。

【会社概要】
株式会社ノンピ
日本から世界へ「共食」の機会と可能性を広げるために「新しい共食の在り方」の社会実装に挑戦中。従来のオフィスワークスペースを食を通じたコミュニティープレイスに変える「nonpi Chef’s LUNCH」、料理と飲み物を全国配送し距離の制約を超えたコミュニケーションを実現するフードデリバリーサービス「nonpi foodbox™」をはじめ、共食にまつわる複数の事業を展開。創業当初に掲げられた「世界から飢餓をなくし、笑顔をふやす」というミッションのもと、テクノロジー・ビジネス・デザインの力で「新しい共食の社会実装」に取り組んでいる。
本社所在地:東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル16F
Webサイトアドレス:https://www.nonpi.com/
「おばあちゃんは、家族と食卓を囲んでいる時間がすごく幸せなんですね」
Q1. 社長の経歴や人となりについて教えてください
上形秀一郎・株式会社ノンピ社長(以下、上形社長) 僕は母方の祖母と両親、弟と妹の6人家族で育ちました。小学校3年生の時に、祖母が脳内出血で倒れてから、大学卒業後に家を出るまでずっと祖母を介護する生活をしていました。子どもながらに入浴介助をしたり、車椅子を押して施設に送ったり、少しでも母の手伝いをしようと思って、僕なりにできることをずっとやってきたという家庭環境でした。
祖母は何度か脳内出血で倒れたのですが、その度に入院すると余計に具合が悪くなっていました。しかし退院して家に戻ってきて、家族みんなで食卓を囲むとすごく元気になるんです。
ある時、主治医の先生が「おばあちゃんは、家族と食卓を囲んでいる時間がすごく幸せなんですね」と仰ったことがあります。その言葉がものすごく僕の中に原体験的に残っていて、人間にとっての生きる喜びだとか、幸せっていうのは、やはり家族であったり、好きな人であったり、人と食事を共にする時間なんじゃないのかなって考えるようになりました。
その後、大学の就職活動のタイミングで「自分が本当にしたいことは何だろう」ということ考えている時に、Facebookの創業者であるマーク・ザッカーバーグさんの「仕事として一番大切なのは、自分が幸せだと思えることを広げていくことだ」という言葉に感銘を受けました。自分の中の幸せ、人間にとっての幸せについて考えた時、祖母のこととシンクロして「やはり食卓を囲むというか、そういう時間が大切だな」と思って、「食」の仕事をすることを決意しました。
しかし就職のタイミングがリーマンショックの時で、大就職難時代でした。就職活動も頑張って、なんとか内定をいただいていたのですが、結局リーマンショックの影響で内定取り消しになってしまったのです。
大学ではドラッカーを学んでいましたのでマネジメントの知識がありましたので、集客などに自信があり、プレゼンコンテストなどにも出場しており、以前から「自分でビジネスをやりたい」という気持ちもあったため、居酒屋の販促支援の会社を起業しました。居酒屋の販促支援でチラシを作ったり集客のパッケージを作ったり、在学中に企業を自分で立ち上げて、もう全部切り盛りも自分で取り組んでいました。
この会社を2年くらい経て、「20代はもっと勉強しよう」と思い、ビジネスを学ぶために監査法人トーマツに入社しました。その頃の業務はフード系のスタートアップの組織開発支援などを行なっており、クライアントさんに経営戦略のソリューションを提案していました。しかし、スタートアップ企業は会社の人間関係がギスギスしているところが多く、いくら提案しても話がまとまらないことが多かったんですね。そんな場合でも最後は「社長と副社長が2人で飲みに行ってください 」と伝え、当事者同士が飲みに行くと全部解決するわけです。ここでも食の力というか、食事をすることの力を実感していたんです。
そんな経験を経て、ちょうど30歳になる年にフード系のメディアサイトのスタートアップに転職しました。この会社でもコミュニケーションの大切さを痛感することが多々ありました。たとえばある部門の空気感が悪い時、みんなで飲みに行って「やるぞ」ってやると一気に前向きになったりするんです。やる気がない社員が多い時は、人事制度を変えたりボーナスの仕組みを入れたりとか、研修をしたりといったことをやるよりも、みんなでご飯を食べに行ったほうが解決したりするんですね。組織課題の多くはコミュニケーションによって解決されるんです。
メディアサイトに携わっていると、次に「やはり本当においしい食事を提供したい」という気持ちがどんどん強くなってきました。僕のバックグラウンドを活かして、法人や「食」マーケットで役に立ちたいという思いもあり、そんなタイミングでノンピの創設者である柿沼(当時社長、現会長)と出会ったのです。
世の中には「食」を知っている人ってたくさんいますよね? 僕は起業した時やトーマツの時から「食」に関するさまざまな会社や個人の方々とお付き合いがありますが、それまでに会ってきた中で柿沼は一番の食通です。彼自身ソムリエですし、本当にジャンルが広くて、日本で最高級の食事から、すごくローカルな食事まで本当にいろんなこと知っていて、食を愛している。「こういう人と一緒に仕事ができたら」と思い、ノンピにジョインすることとなりました。

新しい『共食』を社会実装していく
Q2. 御社の特徴を教えてください
上形社長 ノンピという社名は、イタリア語で「non piu fame」(ノンピウファーメ)が語源でして、英文にすると「no more hungry」、日本語だと「もう腹ペコにしないよ」という意味なんですね。世界中で小麦が取れますし、小麦と言えばイタリア料理ですので、「華やかで美味しいイタリア料理を世界中に届けよう」という考えが原点にあります。
そんな当社が今、会社として掲げているビジョンが「新しい『共食』を社会実装していく」ということ。前述したように「食事を一緒に食べること」が、あらゆる組織課題を解決するし、すごく重要だなと身にしみて感じています。
そもそも人間は生物的にとても弱い生物です。足はウサギより遅いですし、力はゴリラより弱い。歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏の著書『サピエンス全史』では、動物学的に弱い存在である人類がどのように万物の霊長となっていったのかを歴史的事実を元に伝えていますが、人類がこのように発展してきた過程には、「食べる」という目的に向かって組織化・集団化されて発展してきたと思っていて、私たちが掲げている「共食(きょうしょく)」というコンセプトは人間自身の幸せに発展させていくものだと思っています。
基本的に我々が提供しているのは、社員食堂においても1人で早くお腹を満たすような食事ではなく、やはりみんなでコミュニケーションを取れるような社員食堂だというのが基本思想にあります。ケータリング事業も行なっていますがこちらも同様で、みんなで食べる場を提供していると考えています。1人で食事をしたいというニーズもありますが、基本的にはみんなで集まっていいコミュニケーションを取って欲しいですね。
コロナ禍となり共同飲食が否定され、規制されましたが、当社ではそのタイミングでオンライン飲み会向けのフード・デリバリーサービスを開始しました。これも企業が共食を求める願望の現れなんだろう、と思っています。基本的には社員同士で共に食べて、そのコミュニケーションを取り組織化していく、そこからイノベーションを生んでいく、ということを我々はやりたい。こういった思想がベースになってます。
以上のことをふまえ、弊社の社員食堂への取り組みについて、3つの特徴をお伝えします。
まず1つ目がケータリングです。我々は埼玉スタジアム2002のVIPルームのケータリングも提供してますし、国の要職の方々の集まりや芸能人の方などのケータリングも提供しています。しかもすごくファンになって頂いて、毎回使っていただくようになっています。コロナ禍前は、昼は社員食堂で夜は歓送迎会や新年会、ということは当たり前でしたが、そうするとその社員食堂の店長さんにノウハウが片寄ってしまっていました。
その点、今は共通機能としてケータリングチームがあるので、一定の水準で提供できます。このケータリングノウハウがかなりあるので、今運営している社員食堂においても活用していただくことが可能です。具体的には昼間は普通にランチを提供し、夜にその社員食堂の場を使ってケータリングを利用いただく、というものです。
次に、社員食堂専用のモバイルオーダー「nonpi FLIK(ノンピフリック)」です。社員食堂において、並んでる時間よりも、やはりみんなで一緒に食べる時間を多くしてもらいたいので、オーダー時の効率化はどんどん計っていきたいと思います。
3つ目が、キッチンがない「キッチンレス社食」を提供できるということ。裏側の仕組みはケータリングに近いものですが、提供するメニューが社員食堂と変わりがないというのが特徴です。キッチンを作ると防火防水設備、配管投資が必要となり、結構な投資額となりますが、そういう設備が不要でオフィス区画に社員食堂ができるというものです。
これは、他の場所にある社員食堂のアイドルタイムに作った料理を、キッチレス社食サービスの利用企業に運ぶというもの。利用されている企業の社員さんは、自社内で調理されている料理だと思われているようですが、 実は違うんです。コスト面の話もありますが、やはりサステナブルを考えると環境に優しいですね。やはり社員食堂を設置し、その中で調理を行なうことによって排出されるCO2の量は多いので、これからもっと注目されてくると思っています。
社員食堂を基軸として、“人が集まる”ことができる
Q3. ウイズコロナ、アフターコロナにおける社員食堂のメリットについて教えてください
コロナを経て働き方そのものが変わりました。出社が当たり前とされていた働き方は、ハイブッドワークが中心となりました。パーソルキャリア社が2022年7月に行なったハイブリッドワークに関する調査では、個人・企業ともに8割がハイブリッドワークを導入しており、求人への応募時にハイブリッドワークの有無を重視する個人が7割を超えるとの結果が出ています。
一方で、ハイブリッドワークにもデメリットはあります。同調査によると、ハイブリッドワークを導入した個人の半分以上がコミュニケーション不足をデメリットとして挙げています。社内においてコミュニケーション量が不足すると、離職率が高くなったり、仕事の生産性が低くなるなどといったことが指摘されています。社員が離れ、社員の生産性が下がるというのは、企業にとっては死活問題で、当たり前ですが企業は成果を上げることができなくなります。
アフターコロナにおいて、ハイブリッドワークが主たる働き方になると考えていますが、社員食堂はハイブリッドワークのデメリット面であるコミュニケーション不足を解消する最も効果的なソリューションになります。つまり、アフターコロナにおける社員食堂を導入するメリットになります。
社員食堂が、単に腹を満たすための場から社員間コミュニケーションを促す場への変化は、2000年から2020年、つまりビフォーコロナにおいても注目を集めていました。2000年以前、産業の中心が製造業の時代における社員食堂は工場で働く従業員のお腹を安く早く満たすことが役割であり、都心にある本社においても工場の食事と同じような食事が提供されていました。それが2000年以降、IT産業が台頭し、知的労働者の存在価値が加速度的に増す中で、Google社を筆頭に社員間コミュニケーションを促す場としての社員食堂が注目を集めるようになりました。
このように、2000年代から始まったコミュニケーションを促す場としての社員食堂の導入は、ハイブリッドワークのデメリット面であるコミュニケーション不足を解消するために、更なるスピード感をもって社会実装されていくと考えています。

オフィスは仕事をする場からコミュニケーションをとる場へ
Q4. 2023年の社員食堂業界の展望について教えてください
2023年はハイブリッドワーク元年。ハイブリッドワークが本格的に社会実装される年だと考えています。つまり、ハイブリッドワークにおける社員食堂の在り方を、私たちは提案しなければなりません。
この3年、どの企業も、どのくらい出社させようか? テレワークを中心にしようか? 飲み会はどうしよう? 等といった問いに対して、コロナの感染状況を見ながら検討を続けてきました。2023年は、コロナが季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に見直されることも予想されていますが、政府主導での大きな変化は少なくなることが予想されます。
そうなると、多くの企業が2023年以降の働き方について、方針を明確に打ち出さなくてはならなくなります。ビフォーコロナと変わらず、全員強制出社の企業もあれば、オフィスを縮小して全員をテレワークにする企業も出てくるはずです。私は、多くの企業がテレワークと出社を交えたハイブリッドワークが中心になると考えています。
とある経営者は、週3出社が最も社員のエンゲージメントを高め、生産性を高めると話していました。仮に週3出社が主流となった場合、出社したときに多く社員と質の高いコミュニケーションをとってもらいたい訳ですから、できるだけ社員を長い時間社員食堂にとどめたいと思うはずです。そう考えると、社員食堂で提供するメニューは、従来通りのメニューで良いのか? そもそもオフィスをカフェのような空間に変えた方が良いのではないか? これは一例にすぎませんが、新しい働き方に対する社員食堂業界としての提案が求められる1年になると考えています。
また、社員食堂を持っていない会社においても、今まで通り出社した社員にお弁当を配布するだけで良いのか? お弁当を配り、デスクで食べる、それはそれでビフォーコロナにおいては自然な景色だったかもしれませんが、この景色に違和感を持つ社会に変化する可能性も高いと思っています。せっかく出社したのであれば、一人でお弁当を食べるのではなく、コミュニケーションを促すような食事を提供したいと思うはずです。
ただ、社員食堂を作るまでの投資は出来ない、そんな企業向けに弊社ではキッチンいらずの社員食堂ランチケータリングというサービスを提案していますが、ランチケータリングの需要もさらに伸びていくだろうと予想しています。さらに、出社しない社員への食事補助や、出社しない社員とのコミュニケーション機会の創出はどのようにすればよいのか? こういった課題にも、業界として向き合うべきだと思っています。
繰り返しになりますが、世の中の働き方は大きく変化し、ハイブリッドワークが中心となります。その中で、社員食堂業界として、お客様である企業や食べる人の声に耳を傾け、新しい提案をし続けなければなりません。社員間コミュニケーションは、企業における根源的なニーズであり、そのニーズに応える最も効果的なソリューションは一緒に食べること、つまり共食です。私たちノンピは、昨年末に「新しい共食を社会実装する」ことを新たなビジョンとして掲げました。2023年以降、企業における新しい共食を社会実装していくことは、社員食堂業界に求められます。業界の真価が問われる1年になるはずです。
-貴重なお話をありがとうございました。
(聞き手/社食ドットコム編集部)
| 会社名 | 株式会社ノンピ |
| 所在地 | 東京都千代田区一ツ橋1丁目2−2 住友商事竹橋ビル 16F |
| 公式WEBサイト | https://www.nonpi.com/ |