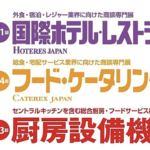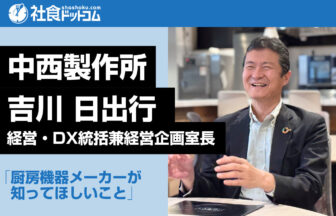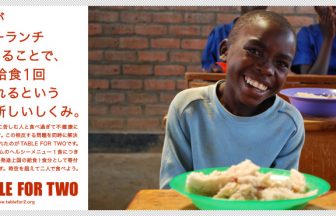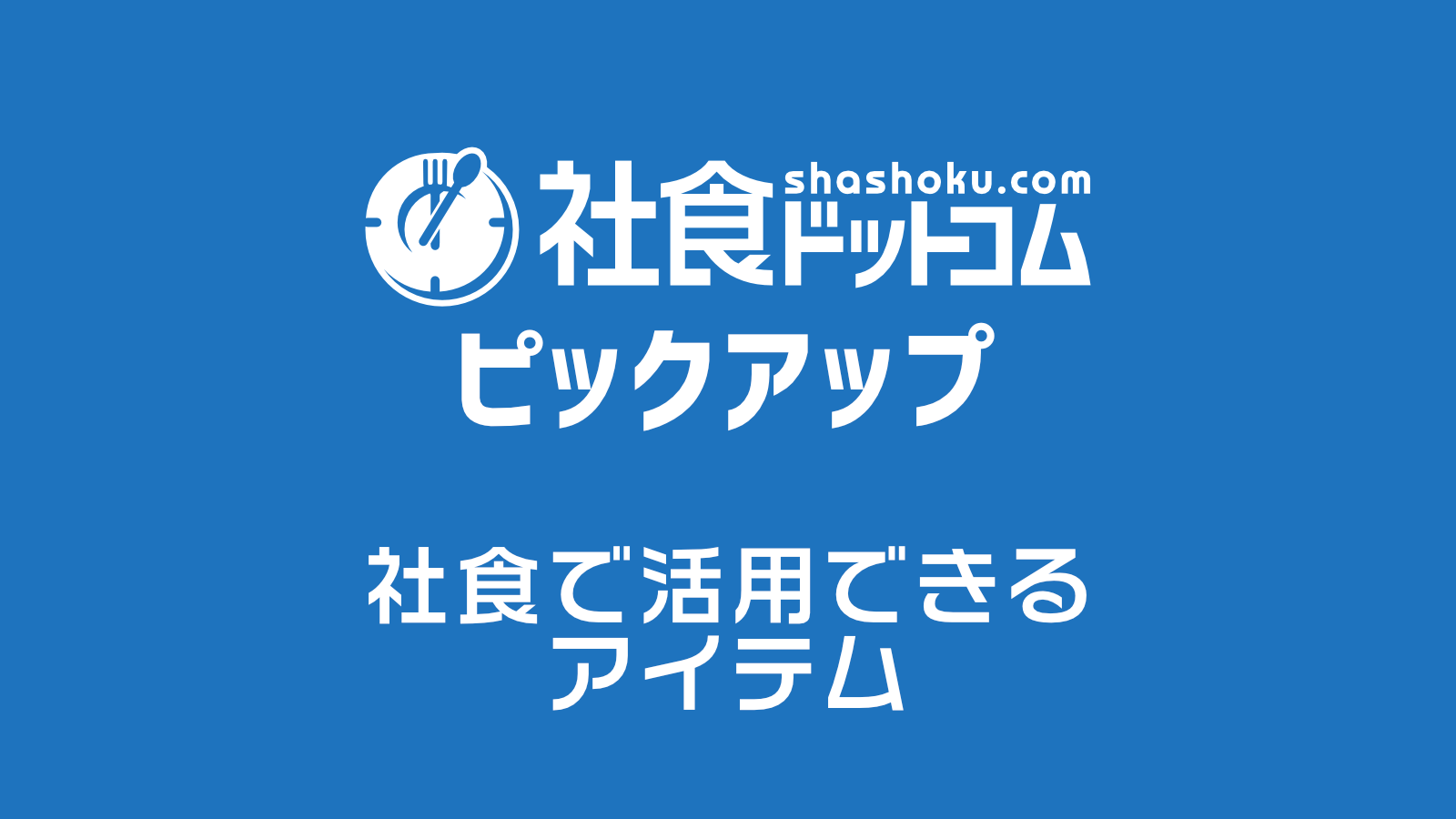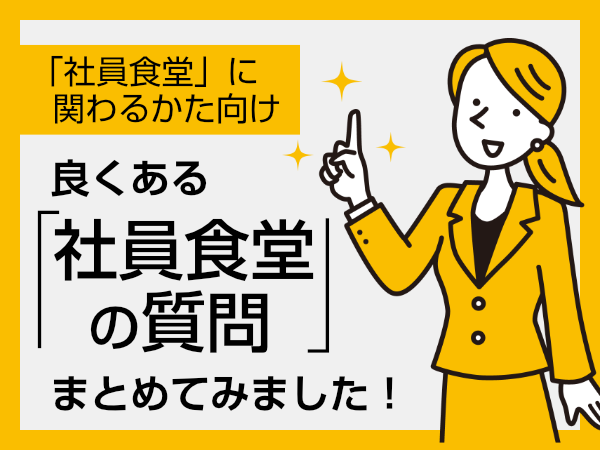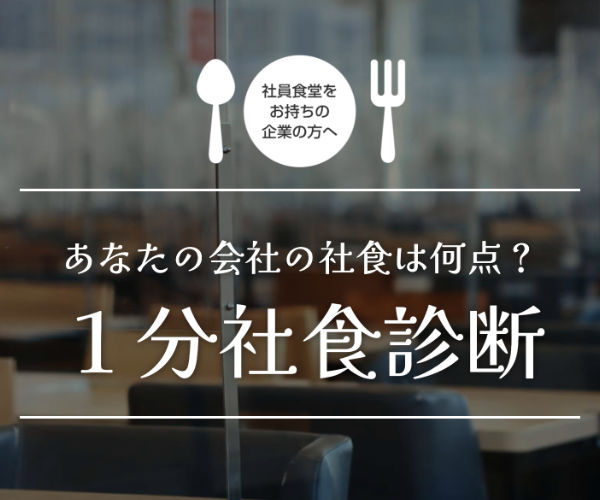昨今は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、出社制限やテレワークの採用が進み、社員食堂そのものの必要性すら問われる時代となっています。しかし不特定多数との接触がないことや栄養バランスの良さ、社員同士のコミュニケーションの場となるなど社員食堂のメリットについてはあまり語られることがなく、社員食堂を有していない企業の方々には、その実情が届いていないことが懸念されます。
このような中、社食ドットコムでは、社員食堂運営会社のトップの方に「社員食堂の良さ」を発信していただき、社員食堂の必要性を社員食堂を有していない企業の方々に理解していただき、社員食堂の市場拡大につなげることが業界全体のメリットに繋がると考えています。
そこで、社員食堂運営業界にて長らく活躍されている社員食堂運営会社のトップの方を直撃取材。「トップが語る、2023年の社員食堂業界」をテーマとして、社員食堂のメリットはもちろん、社長の人となりから今後の社員食堂がどのようになっていくのか? などについてお話をうかがいました。
今回は、シダックスコントラクトフードサービス株式会社の佐藤好男社長です。
【プロフィール】
佐藤 好男(さとう・よしお)
シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役社長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役社長。1977年4月に、現在のシダックスコントラクトフードサービス株式会社であるキャフトフードサービス株式会社に入社。その後、同子会社やシダックスグループの事業子会社の取締役を経て、2013年6月には常務監査役に就任。2020年4月より現職。

【会社概要】
シダックスコントラクトフードサービス株式会社
1960年5月設立。オフィス・工場などの社員食堂、学校などの学生食堂の受託運営をメインに、学生寮・社員寮、レストラン、売店の受託運営も行う。全国に9カ所の支店、5カ所の事業所。連結売上1,155億2,500万円、従業員数約40,000人(2022年3月時点)。
本社所在地:東京都渋谷区神南1-12-10 シダックス・カルチャービレッジ。
Webサイトアドレス:https://www.shidax.co.jp/
とにかく人と話がしたい、人が好き
Q1. 社長の経歴や人となりについて教えてください
佐藤好男・シダックスコントラクトフードサービス株式会社社長(以下、佐藤社長)
私自身も食べることが好きだったことと、日本にまだ自分で食べたいものをチョイスするというアメリカ的な社員食堂がない時代に、カフェテリア形式の社員食堂に取り組んでいた会社で、この新しいものに向かっていくという会社の姿勢にも惹かれ、これは面白いな、というところから1977年にキャフトフードサービス(1994年にシダックス株式会社に社名変更、現在のシダックスコントラクトフードサービス株式会社)に入社し、今年で46年目になります。
私自身どちらかと言うと本社より現場が好きだったので、入社してすぐに「現場に行かせてくれ」と頼み込んで1年半ぐらい現場にいました。現場ではお客さんと直接会えるということもあり、楽しかったですね。
その後営業開発となり、当時は川崎エリアを新規開拓するということで、自社のパンフレットと地図を持って朝一番で駅に着いたら、そこから次の駅まで歩いて工場やオフィスビルをアポなし訪問をするわけです。しかし当時は会社の知名度も低く、誰も話を聞いてくれず、100%門前払いでした。
とにかく人と話がしたいのに、誰も話を聞いてくれない。そこでどうするか? と考え、翌週からは会社の入り口にいる守衛さんと話すことを目標としました。守衛さんのところに行って「ここの会社の食堂はどうですか?」とヒアリングするわけです。すると守衛さんが「誰々さんならその話を聞いてくれるかもしない」と言って、いきなり総務の課長さんと繋げてもらったりする機会ができるようになってきたのです。なかなか仕事には直結しませんでしたが、大変勉強になりましたね。
その後、静岡県浜松市、名古屋市に転勤となり、各地で新規取引業者の選定を行なうなど自分なりに正しいと思ったことを推し進めました。そんなある日、現場にいたところ電話がかかってきました。「佐藤君か? シダだ」と。「シダって誰?」と思っていると、なんと創業者である志太社長(当時)からでした。電話の内容は「佐藤くんか、君には八戸に行ってもらう」とのことでした。たまたま八戸を含めた東北地域の営業開発担当者が異動になるということもあって、青森地区を強化したいということで声をかけていただいたのです。
新幹線もなく、まだまだ交通の便も悪かった時代。東北への辞令を栄転と捉える人はいなかった頃ですので、このまま辞めてしまってもおかしくはなかったと思います。ただ、志太社長本人からの電話だったことで、「志太さんから直の電話だなんて光栄だ」とも思ったのです。「はい、わかりました」と快諾し、26歳になる時に青森の八戸に地区マネージャー代行として赴任しました。
その後、首都圏のスーパーバイザーを2年、甲信地区の立ち上げの3年を経て本部の本部長を3年、そして東海支社の支社長として浜松へ1年半。また本部に帰ってきたら社内のカンパニー制にするということでバイスプレジデントになり2年。メディカル事業本部をやって、カラオケ事業に常務として3年とキャリアを重ねてきました。そこでも自分の正しいと思うことを貫いていたら、現場関係から外すとなって、シダックス株式会社の監査役を7年。監査役になっても言いたいこと言うもんだから、フード全体を見ることになって現場復帰したのが3年前です。
赴任地の浜松も名古屋も、八戸も松本も大好きな街になりました。在任期間が短かくても、先方の栄養士さんが可愛がってくれたり、パートさんが夕飯を作ってくれたり、行く先々でお世話になるというか、不思議とそういう人が出てきてくれる。会社にも好きな上司や先輩がいっぱいて、仕事をその人たちにも教えてもらったり、お客さんからも教えてもらったりしました。
そういう意味では、私は非常に人に恵まれています。でも一歩懐に入らないと、なかなか教えてくれませんよね。だからそのきっかけが謝罪であってもいいと思うんですよ。なにかクレームがあったら「俺の出番だ」っていうように、そういったことも逆に期待していました。私の名前が「好男(よしお)」ということに関係しているのかもしれませんが、人が好きなんですよ。だから親しくなると「よしお」ではなく「すきお」になってしまうんです(笑)。
会社人生では、いつも3年ぐらいすると別会社のような環境の違うところへ追いやられてきたけれど、大変な場所のほうが改革ができるのでワクワクします。何か問題があった時のほうが使命感に燃える性分なんです。だから現場に行って先方さんと店長が仲良くやっているのを見ると、もちろん嬉しいんだけど、私が来なくてもよかったんじゃないか、と少し残念な気持ちになりますね(笑)。

お客様に育てられて成長した会社
Q2. 御社の特徴を教えてください
佐藤社長 当社は創業期から「お客さまに寄り添う」「一緒になって解決しよう」という原理原則を掲げています。やはりお客さまとの契約なので、安心・安全だとかSDGsといった取り組みがあるわけですが、そこにはお客さんに喜んでもらうということ、そして食べていただいて「おいしかったです」という顔が見たいわけです。そうすると努力のしがいがあったなと思うでしょう。
お客さんが「シダックスで良かった」って言ってもらうには働く人が元気でないとダメだし、社員食堂と外食の違いは、お客さんのわがままを聞くことができるのが社員食堂だと思っています。そういうクライアント企業とのキャッチボールも笑って話せる関係にしたいと思っています。そうすると、何があっても前へ進む会話ができると思うんですよね。そういった教育について、担当する店長にしてもスーパーバイザーにしてもしっかりと力を入れているところです。
我々の仕事というのは契約ビジネスで、「お客様の懐に飛び込め」というのが創業者の信念の中にあります。だから振り返ってみると、お客さんに育てられて成長してきた会社だという気持ちが強いですね。
社員を様々なリスクから守れる唯一無二の設備
Q3. ウイズコロナ、アフターコロナにおける社員食堂のメリットについて教えてください
佐藤社長 1点目として、コロナが収束してもリモートワークなどが定着し、社員同士の繋がりが希薄となる中で、社員食堂は、お互いがコミュニケーションを取れるとても重要な施設だと思います。専門事業者が運営し、感染症対策や衛生的に管理された施設でコミュニケーションが取れる唯一の場であり、社員も企業側も安心し、リラックスしながら社員同士の繋がりを強化できることか最大のメリットと考えます。
2点目としては、企業は在宅勤務による体重の増加など、健康管理に課題が上がっていると伺っております。そこで社員食堂で健康的に配慮され、栄養管理された食事を提供することで、社員への健康に対する啓発活動や注意喚起につながり、社員が健康になることで会社に活気があふれ、業績アップにもつながると考えております。
3点目としては、各企業様も取り組んでいらっしゃると思いますが、SDGsの取り組みの一環として社員食堂を活用することが挙げられます、弊社では環境保全活動の一環として、食品ロス、廃棄ロスの軽減や、持続可能な水産物(ブルーシーフード)の使用、代替えミート普及の取り組みなどで、社員食堂利用者への啓発活動を行っており、利用者も自分もSDGs・社会貢献活動に参加している意識が高まり、各企業様でのSDGsの取り組みも従業員参加型で飛躍的に進むと思います。
最後に、社員食堂は健康管理、感染症対策がしっかり施され、衛生的にも安心・安全な食空間であり、誰が、いつ、どこで、何を食べたか、利用履歴が確認できる唯一の施設です。社員を様々なリスクから守れる唯一無二の設備であることが、最大のメリットではないでしょうか。

ニューノーマルの中で強まる福利厚生の考え方
Q4. 2023年の社員食堂業界の展望について教えてください
佐藤社長 私が社長に就任して名刺もたくさん作って、「全国に挨拶回りにいくぞ」と言っていたら、すぐにコロナ禍になってしまって、各地の現場から逆に「きてもらったら困る」という状況になってしまいました。今でも入所制限があるところがあるなど、コロナ禍はまだまだ落ち着かない状況です。
それに伴い社員食堂のあり方も変わってきましたね。ただ、いわゆるニューノーマルという中でも福利厚生の考え方は逆に強くなっています。社員間のコミュニケーションの必要性が高まり、「社内運動会をやろう」とか「新年会をやろう」といった、リアルでのイベントをやりたいという声があちらこちらから聞こえてきます。
このようなコロナ禍においては、2019年以前のやり方とは違った、新しいコミュニケーションの場を企業側も求めてます。特にオンラインでの会議などについては、余分なことや細かいことまで話しませんので、微妙なニュアンスまでは伝わらないですよね。やはりそういうキャッチボールというのが大事なので、そういった状況を改善するのが社員食堂の役割となっていくでしょう。
社員食堂というのは11時から14時くらいまでを利用する場合が多いですが、その間だけのために高い賃料を払うのは勿体無い、そこをどう活性化して付加価値をつけるか? 特にオフィス系の社食はどう付加価値がついて、社員食堂があることによってのプラスアルファと食堂をどう未来型にしていくかっていうことが問われています。
そんな中で、「企業」と「喫食する従業員」と「提供する社員食堂運営会社」の3者がうまく擦り合わせる必要があります。みんながwin-winになるにはどうすれば良いのか? ということです。どこかが良くてどこかが苦しんじゃうような、誰かが「そんなはずじゃなかった」とかっていうことになってしまってはいけない。企業様や喫食者様に喜んでもらえても、提供する社員食堂運営会社が犠牲になっていてはならないし、3者がうまく協力しあって、企業様の考え方、従業員の関係だったり社員食堂運営会社の職場に対する考え方、この3者が本当に腰を据えてじっくりと相談・提案しながら進めていくわけです。
企業様にとって社員食堂はコストがかかります。自らの会社の中に社員食堂を置くということは、従業員の健康を考えているし、安心・安全な食材も含めて提供しているということです。ですので社員食堂がある企業は、会社が従業員を大事にしているということに直結します。企業が優秀な人材を確保するために、社員食堂の必要性も高まっていくことでしょう。
-貴重なお話をありがとうございました。
(聞き手/社食ドットコム編集部)
| 会社名 | シダックスコントラクトフードサービス株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-12-10 シダックス・カルチャービレッジ |
| 公式WEBサイト | https://www.shidax.co.jp/ |