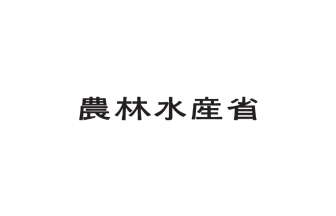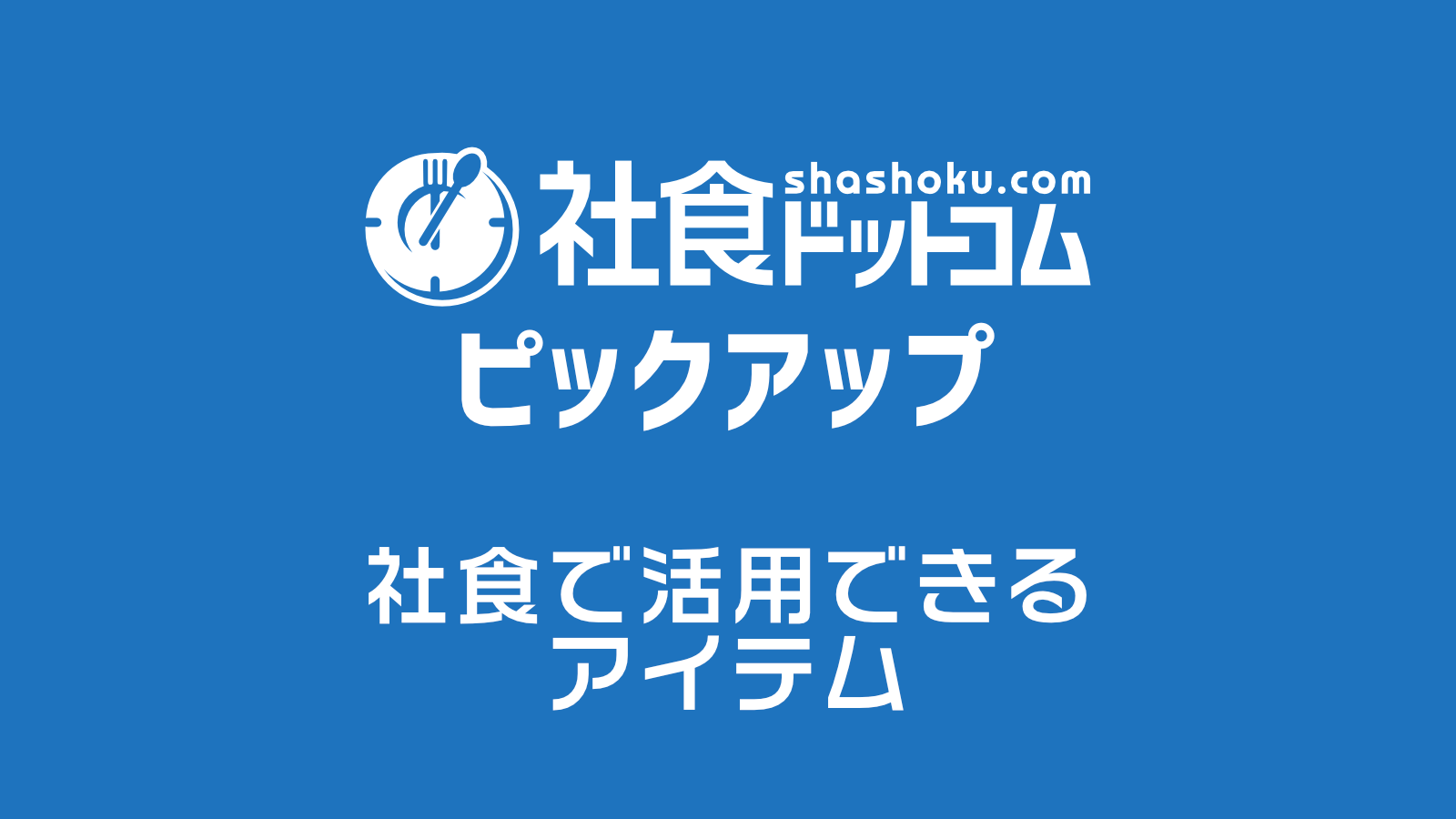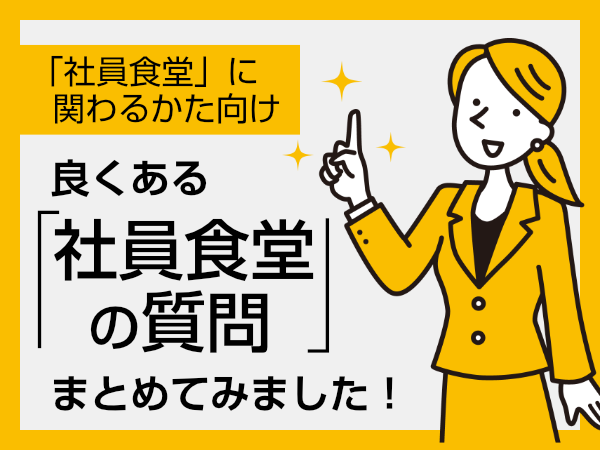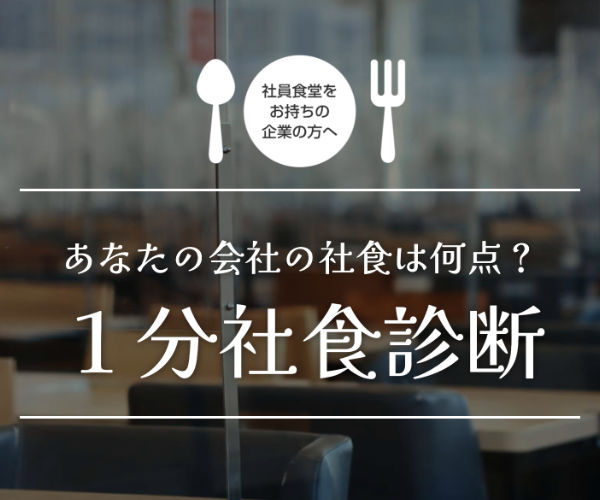1881年、神戸異人館のハンター坂の由来でもあるE.H.ハンターが大阪安治川岸に操業したのが日立造船の前身である“大阪鉄工所”です。同社は1890年には日本で初めての鋼船「球磨川丸」を建造するなど、エンジニアリングとものづくりで日本の造船事業界を牽引してきました。その後1936年に日立グループ傘下に加わり、1943年に社名を現在の日立造船株式会社に変更しますが、戦後に財閥解体の対象となり日立グループから独立。さらに2002年に造船事業を分離しており、現在はごみ焼却発電や上下水道施設などのプラント製造、精密機械製造、防災・社会インフラといった事業を展開しています(資本金約454億円(2018年9月30日現在)、年商(連結)3,764億円(2018年3月期)、従業員数(連結)10,747名(2018年9月30現在))。
日立造船の大阪本社は、大阪湾に浮かぶ人工島咲洲にあり、社員食堂は約1300m2という面積で一日約1000食が提供されています。今回は同社の社員食堂をご案内いたします。

大阪湾の人工島咲洲(さきしま)にある日立造船本社ビル。大阪メトロ中央線の終点となるコスモスクエア駅が最寄駅。 
本社社屋の横に建てられているA.I/TECは、遠隔監視およびIoT(Internet of Things)、ビッグデータ、AI(人工知能)などのICT活用の拠点となっています。 
会社の敷地内にある神社。安全祈願は欠かせませんね。 
天井の高い1階にある打ち合わせスペース。毎日多くのお客様との打合せが行われております。 
会社で行っている事業や、企業年表がディスプレイされており、会社概要がわかるようになっています。ふーむ、メモメモ。 
受付周辺には厚労省より「子育てサポート企業」と認定されたマークや、熊本で地震があった際に支援したことから贈られたくまモンの感謝状などが。 
2階にある社員食堂へ行ってみましょう。陳列棚にはその日のメニューが並べられているだけでなく、掲示板を使った食のワンポイント情報なども。 
支払いは社員証で精算し、給与天引きです。プリペイドカードでの支払いもできます。 
食堂のマップが示されているだけでなく、その週のメニュー一覧やイベントの案内なども掲示されています。 
食堂の座席数は620席。食堂全体の広さは約1300m2。 
ピークタイムとなる12時に向けて、スタッフの方も急ピッチで準備中。 
メインメニューと合わせると、一日に必要とされる野菜摂取量の一食分以上の野菜量が摂取できる“健康小鉢”。 
人気メニューのひとつ「かけうどん」に付けるトッピングも豊富。 
食堂の壁には会社の創業期の様子が描かれた絵画があり、会社の歴史を感じることができます。 
社員食堂の営業時間は11:00~13:30と17:35~18:30(うどん、小鉢のみ)。 
食堂以外にも喫茶室があり、そちらの営業は7:45~8:50(モーニングセット)。11:30~13:30(ドリンク)。 
そろそろ人が列をつくってきました。メニューは社内イントラネットにも掲載されています。 
定期的に各職場の代表が集まって、食堂について話し合う給食委員会が開催されており、その場で改善出来る点は改善しているとのこと。 
週に1回、ご当地メニューや有名店とのコラボメニューといったイベントメニューを実施しています。 
社員の特徴は“がっつり食べたい!”人が多いそうです。 
天井は波のようなデザインを取り入れています。これは“海”に関連した事業を行っていたことを表しています。 
食材も可能なものは近隣エリアから調達。地産地消で地域貢献も行なっています。 
【ヘルシーメニュー】豚肉の生姜焼きセット
カロリーやコレステロール値、塩分を制限しています。
【Aランチ】チキントマト煮 
【Bランチ】豆腐ハンバーグ柚子風味ソース 
【麺】かけうどん (かき揚げ、茄子の天ぷら) 
【Voice】開放感のある広い食堂で毎日おいしく食べてます。栄養バランスが良いのでキチンと食べることが大事だと思います。 
【Voice】社員と話す機会が持てるので、食堂はコミュニケーションを取る場所でもありますね。 
【Voice】同期と一緒に食べて、仕事だけでなくプライベートの話もします。研修で本社にきている人とばったり会うことがあります。 
【Voice】うどんは安いこともあり人気で並びますね。イベントのご当地メニューがもっと増えると嬉しいです。 
【Voice】働いている人のサービスはすごくいいんです。作業が速やかですし話しやすいですね。 
食後はこちらへ下膳。利用者が多いため混み合った際は棚に置いていきます。 
創業者E.H.ハンター像の前で。ご案内いただいた人事部労働・福祉グループの小川さん、総務部広報グループの永原さん(左から)。
まとめ
日々改善し、バージョンアップし続ける日立造船の環境配慮型社員食堂
日立造船は「エネルギー」および「水」に関わる事業を通じて、循環型社会実現に向けて環境問題や食料・水・エネルギー問題にチャレンジし続けており、SDGs(持続可能な開発目標)の取り組みで豊かで活力のある未来を創ることを目指しています。
そんな同社の社員食堂でもっとも意識している点をうかがうと、
「会社としての方向性と同じなのですが、環境に良い社員食堂づくりを第一に考えています。売れ残ると食品ロスとなり廃棄することになりますので、食品ロスを出さないように、社員の食事の傾向などをデータ化し把握するようつとめています。ただ、職員が好む食事ばかりでは健康づくりの側面で問題がありますし、売り切ればかり続くと食べられなかった社員が困るので、食材の選定から考えてメニューづくりを検討しています」とのこと。
また、「健康面では、必要な野菜量が摂取できるように、“メインメニュー”と“小鉢”をあわせて食べると、野菜が125g以上になるようにメニューを用意しています。これは厚生労働省が推奨している1日の野菜摂取量350g以上の1食分となるようにとの配慮です。加えて、エネルギーの過剰摂取や肥満を防止するきっかけづくりとして、ヘルシーメニューを週1回のペースで提供しています。また、定期的に各職場の代表が集まって、食堂についての改善点を話し合う給食委員会を開催しています。その中で出た意見をもとに、カレーうどん・そばの提供を始める等の試みをしており、時間が経つほど自社らしい食堂になってきていると感じています」(人事部 労働・福祉グループ/小川氏)とのことです。
自社の事業内容と合致した方向性、そして社員の健康も考えた日立造船の社員食堂でした。
大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
記事の内容は取材および掲載時点の情報であり、最新の情報を反映・担保するものではありません。
【企業リリース】2019/08/28 人事異動